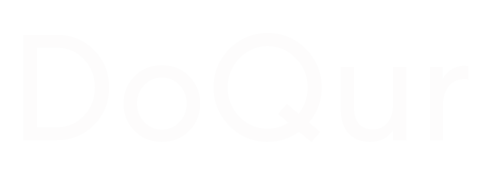Search フランツの自由 result, Total 382967 (take 0.001275 seconds).
Ngokmixhpss review on 婚約者の友人.
1919年ドイツ
フランスとの戦いで
婚約者フランツを亡くしたアンナの元に
フランツの友人 アドリアンが現れる .
何故会いに来たのか…
『彼を知れば知るほど好きになる』
『君に許しを請いに…解放されたくて…』
アドリアンに惹かれはじめるアンナ
.
養父母の優しさ
気遣うアンナ
アドリアンの罪な純粋さ
読めなかった展開
そして
美しい映像・美しい音楽・美しい...
Tttreeeaws review on 婚約者の友人.
1919年のドイツ、婚約者フランツを戦争で失ったアンナは毎日、お墓参りをしていた、ある日、見知らぬ男が墓の前で泣いているのを目撃する。
話を聞くと、パリでの友人でアドリアンといい、墓参りに来たという。
フランツの両親とアンナは生前の様子が聞けて喜ぶ。
アンナは次第にアドリアンにひかれていくが、アドリアンには隠していることがあった。
善人が戦争でたどる道のよう...
ffhowex review on 17歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン.
本当にどんな役にも入り込んで、その役として
スクリーンに生きている。彼の存在感がこの映画を生きたものにしている。
フランツの夢のシーン、自殺するコミュニスト、ナチスの旗がオットーの片足が短くなったズボンに替えられている所、重苦しさと幻想が入り混じり、タバコのような苦さを感じた。
rzxxiz review on 17歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン.
ネタバレ! クリックして本文を読む
ーナチスの忍びよる影が色濃くなってきた、1930年代のウィーンが舞台ー
■印象的なシーン
・”坊や”フランツが働くことになった、オットーの芯の通った男振りと、キオスク店内の装飾に惹かれる。
ーえ、タバコ屋なのに、文房具も、”そんなもの”まで、売っているんですか!。
オットーの”タバコ屋は、味わいと悦楽を売る場所だ・・”に...
Etenhiluoyastqh review on 婚約者の友人.
フランソワ・オゾン監督が初めてモノクロに挑戦し、1919年のドイツを舞台に、アンナ(パウラ・ベーア)の戦死した婚約者の友人アドリアン(ピエール・ニネ)との交流をミステリアスに描いた人間ドラマ。時々カラー映像に変わるという手法で、カラーになった時はアンナの精神状態を投影しているかのように感じるが、ハッキリとはわからない。
ヒロインであるアンナが婚約者フランツ...
Kxiognmssph review on ルートヴィヒ 完全復元版.
庶民は財産もなく不自由な生活で、王侯貴族は派手で自由な印象だが、自由については、有象無象は法律がなければ無制限であり、稀少な存在程、制限され不自由になる。自由度の高い者の発言は軽く、不自由な立場の者の発言は重い。この為に稀少な王侯貴族、俗世なら社長や首相の命令は相当な重さを持つ。神に至れば絶対だが、一部は道徳や常識になっている。
zznazo review on グッバイ、レーニン!.
最後のほうで家族みんなでドライブに出かける。その車のデザインの先進的なこと。まるで21世紀の水素自動車やハイブリッド車を思わせるデザインではないか!
多くの人々が自由を待ち望んだのだろう。決して少なくなくはない数の人が共産党政権下で思想や身体の自由を奪われていたことだろう。
しかし、西側が自由だったのかと言えば、そうとは言えない。
市場原理によって、登場人...
gfqchx review on メン・イン・ブラック2.
最後の自由の女神が一番やりたかったのかなって
Laoebenmsg review on 婚約者の友人.
ネタバレ! クリックして本文を読む
アドリアンには
嘘をついたままでいて
欲しかったですね。
アンナは
本当に
許せたのか?
ドイツもフランスも
戦争で家族を亡くしているのは
一緒なのだ...
フランツのお父さんが
酒場?でのシーン
「子供を戦争に行かせて
敵国の兵士を殺させて
父親は祝杯をあげる」みたいなぁ〜
何とも言えないセリフでした。
今回...
Stacfhictr review on ジミー、野を駆ける伝説.
自由を得るためには戦いが必要なのだ。そう思い知らされる。作品の中の宗教の存在は既成概念と解釈することができる。今も昔も古いものと戦わないと、我々に自由は無いのだ!
Rueesybhvr review on ルートヴィヒ 完全復元版.
尺が237分、「愛のむきだし」と同じだ。
内容さえ良ければ(支持が得られれば)、この長さでも受け入れられるんですね。
国王ルートヴィヒの人生、本作で照射されているのは、社会的動物としての人間と自由についてなのではないか、と私は思いました。
自由とは何か、自由であることの代償は何か、そして、人は、観客であるあなたは、自由を希求しているか。
そんなことを考えなが...
Nsxophgsimk review on 駆込み女と駆出し男.
今とは比較にならないけど、弱者を救う手立てがあってよかった。
離縁の理由も千差万別。不自由さと理不尽さで駆け込むものもいれば、生き方の自由さを求める人もいたんだと。